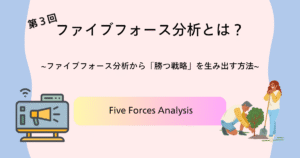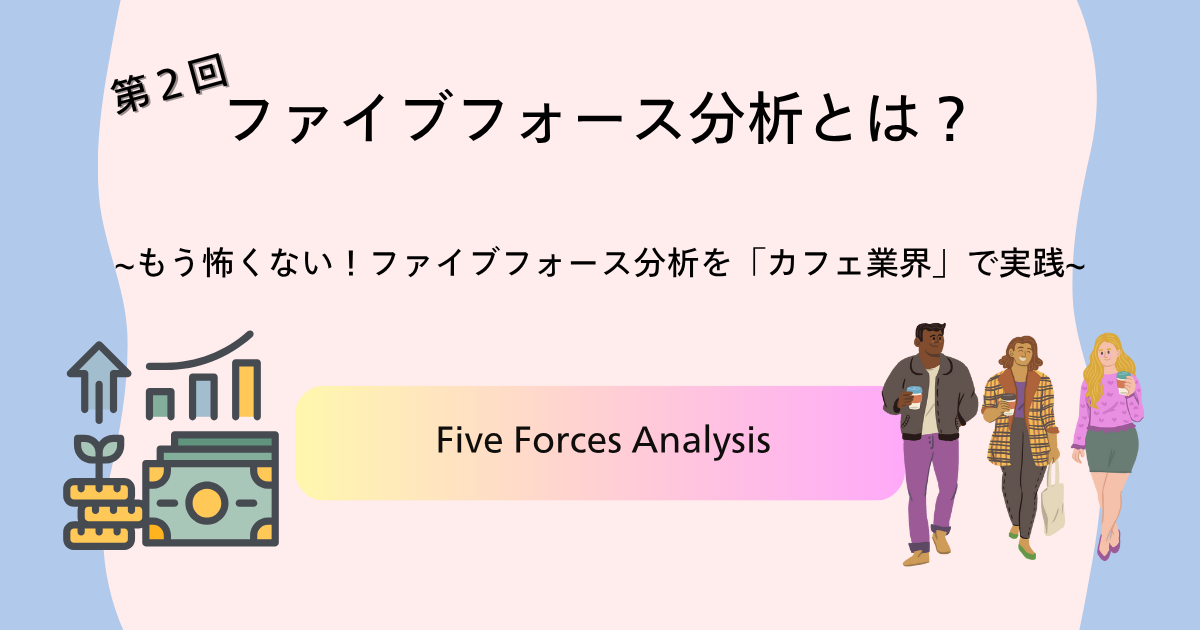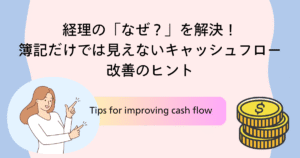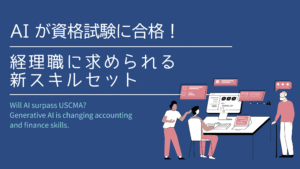こんにちは、USCMA(米国公認管理会計士)のくんぺいです!
前回の記事では、ビジネスの収益構造を解き明かす強力なツール「ファイブフォース分析」の基本的な理論について解説しました。
「理論は分かったけど、これをどう仕事に活かせばいいの?」
そう感じている方も多いのではないでしょうか。フレームワークは、知っているだけでは意味がありません。実際に使ってみて初めて、その真価が分かります。
また、このファイブフォース分析は、ビジネスの現場だけでなく、USCMA(米国公認管理会計士)のような国際的な資格試験でも非常に重要視されています。
そこで今回は、理論から実践へ! 私たちにとって非常に身近な「カフェ業界」を題材に、ファイブフォース分析を体感してみましょう。なぜあのカフェはいつも賑わっているのか、なぜ価格競争が激しいのか。
その裏側にある力学が、きっと見えてくるはずです。
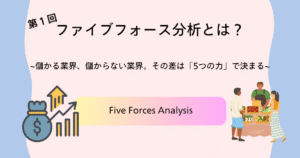
目次
分析の前提:カフェ業界の定義
分析を始める前に、今回対象とする「カフェ業界」の範囲を明確にしておきましょう。
- 対象:コーヒーや紅茶、軽食などを店内で提供することを主たる事業とする店舗。(例:スターバックス、ドトール、個人経営カフェなど)
- 対象外:レストランのドリンクバー、コンビニのイートインスペース(これらは後述する「代替品」として扱います)
では、このカフェ業界を取り巻く5つの力(脅威)を分析していきましょう!
カフェ業界のファイブフォース分析

① 業界内の競合の脅威【非常に高い】
カフェ業界の最も大きな特徴は、業界内の競争が非常に激しいことです。
- 大手チェーンの存在:スターバックス、ドトールなど、ブランド力と規模の経済で優位に立つ強力なプレイヤーが多数存在します。
- 多様な競合:昔ながらの純喫茶、こだわりの豆を売りにする個人経営のカフェ、コワーキングスペースを兼ねたカフェなど、様々な形態の競合がひしめき合っています。
- 競争の軸:価格だけでなく、居心地の良さ(Wi-Fi、電源)、メニューの独自性、ブランドイメージ、立地など、競争は多角化しています。
【結論】 プレイヤーが多く、差別化の軸も多様なため、業界内の競合の脅威は「非常に高い」と言えます。
➡️ USCMAの視点:これはまさに『業界内の競争が激しいと、値下げ合戦や広告費の増大で、収益性が低下する』という原則を体現しています。
② 新規参入の脅威【高い】
次に、新しいカフェがこの業界に参入するハードルの高さを見てみましょう。
- 参入障壁は比較的低い:
- 資格・許認可:飲食店営業許可などの取得は、他の業種に比べて比較的容易です。
- 初期投資:個人で小さな店舗を始める場合、莫大な初期投資は必ずしも必要ありません。
- 一方で困難な点も:
- ブランド構築:多くの競合の中から選ばれるためのブランドを確立するには時間とコストがかかります。
- 好立地の確保:大手チェーンが駅前などの一等地を既に押さえているため、有利な立地を見つけるのは困難です。
【結論】 開業自体のハードルは低いものの、競争の激しい市場で生き残るのは容易ではありません。そのため、新規参入の脅威は「高い」と言えます。
➡️ USCMAの視点:試験では「参入障壁は高いか低いか?」が問われます。この業界の場合、開業の障壁は低いですが、収益化の障壁は高いと分析できます。『新規参入の脅威が高いと、新しい競争相手が次々と現れ、価格競争が激化し収益性が低下する』という理論に直結します。
③ 代替品の脅威【非常に高い】
「カフェでコーヒーを飲む」という目的を代替できるものは、驚くほど多く存在します。
- コンビニコーヒー:最大の代替品です。「安くて、早くて、そこそこ美味しい」という価値で多くの顧客を獲得しています。
- 家庭や職場:自宅のコーヒーマシンや職場のコーヒーメーカーも強力な代替手段です。
- その他:ファミリーレストランのドリンクバー、自動販売機、ペットボトル飲料など、選択肢は無数にあります。
【結論】 顧客は「カフェに行く」以外の選択肢を非常に多く持っています。したがって、代替品の脅威は「非常に高い」レベルです。
➡️ USCMAの視点:これも重要なポイントです。『代替品の脅威が高いと、顧客が他の製品やサービスに流れやすく、価格を上げられず収益性が低下する』のです。カフェは単なる飲料提供以外の付加価値がなければ生き残れません。
④ 買い手の交渉力(顧客の力)【高い】
買い手、つまり私たち顧客が持つ力はどうでしょうか。
- 顧客の交渉力は強い:
- 選択肢の多さ:競合店や代替品が多いため、顧客は簡単に店を変えることができます(スイッチングコストが低い)。
- 情報へのアクセス:口コミサイトやSNSで店の評判を簡単に調べられるため、価格や品質にシビアな判断を下せます。
【結論】 基本的に顧客は多くの選択肢を持っているため、買い手の交渉力は「高い」と言えます。顧客を満足させ、リピーターになってもらう努力が不可欠です。
➡️ USCMAの視点:セオリー通り、『買い手の交渉力が強いと、値下げ圧力や品質要求が厳しくなり、収益性が低下する』という構図が明確に見て取れます。
⑤ 売り手の交渉力(サプライヤーの力)【低い】
最後に、カフェにコーヒー豆や食材を供給する業者(サプライヤー)の力を見てみましょう。
- サプライヤーの交渉力は弱い:
- コーヒー豆:世界中に多くの生産地や卸売業者が存在するため、カフェ側は仕入れ先を選べる立場にあります。
- 食材:牛乳や砂糖なども同様に多くのサプライヤーが存在し、特定の業者に依存する必要性は低いです。
【結論】 一般的な食材やコーヒー豆の調達においては、売り手(サプライヤー)の力は限定的です。そのため、売り手の交渉力は「低い」と言えるでしょう。
➡️ USCMAの視点:これは企業にとってポジティブな要因です。『供給者の交渉力が弱い』業界は、原材料費などのコストをコントロールしやすく、収益性を確保しやすい側面があることを意味します。
カフェ業界の全体像とUSCMA試験への応用
業界全体の収益性
今回の分析をまとめると、カフェ業界は「売り手の交渉力」以外の4つの力が非常に強く、自社にとって厳しい方向に働いていることが分かります。
これは、全体として収益を上げにくい、非常に厳しい業界であると言えます。
USCMA受験者向け:シナリオ問題への応用
今回の分析は、USCMAのシナリオ問題にそのまま応用できます。
- 問いの例①:「カフェ業界の収益性に最も大きな影響を与えているのは5つの力のうちどれか?」
- 解答例:「業界内の激しい競争」と「代替品の脅威」の2つが特に大きい。なぜなら、無数の競合店とコンビニコーヒーなどの代替品が存在するため、価格競争に陥りやすく、独自の付加価値を提供しなければ顧客に選ばれないからである。
- 問いの例②:「ある企業のカフェ事業の収益が悪化した原因をファイブフォースの観点から分析せよ」
- 解答例:収益悪化の原因として、近隣に大手チェーンが出店したことによる「業界内の競争の激化」や、コンビニ各社が高品質なコーヒーを提供し始めたことによる「代替品の脅威の増大」などが考えられる。
上記の例題は、USCMA試験の出題傾向に基づいて作成した練習問題です。
このように、具体的なシナリオをファイブフォースに当てはめ、各要因が収益性にどう影響するかを論理的に説明する能力が、USCMA試験では求められます。
まとめと次回予告
いかがでしたでしょうか。今回は「カフェ業界」を例に、ファイブフォース分析を実践し、それがUSCMA対策としてどう役立つかを解説しました。
ただ用語を暗記するのではなく、このように身近な業界に当てはめて考えてみることで、知識は一気に「使える武器」に変わります。
さらに、この分析力は試験対策にとどまらず、実務でも大いに応用可能です。
たとえば、事業計画の立案や新規投資の評価、競合他社の動向分析など、管理会計が求められる現場では常に「収益性に影響を与える要因を見抜く力」が問われます。
今回のようなシナリオ思考を身につけることで、現場でも即戦力として活かすことができます。
このような実践的な思考こそ、USCMA試験の合格に繋がるだけでなく、“数字で経営を語れるプロフェッショナル”への第一歩です。
▼次回は、この分析結果から具体的な戦略を立てる方法について、さらに深掘りしていきます。お楽しみに!