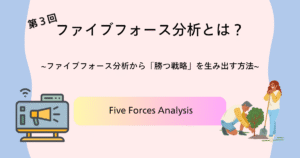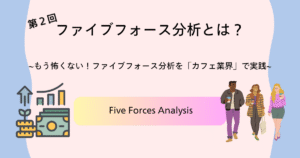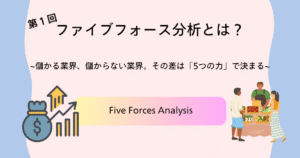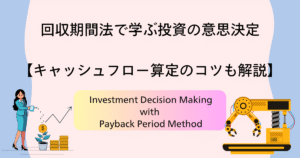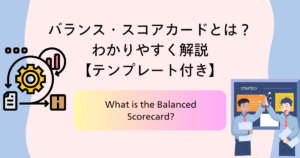― USCMAが導く“使える会計”の第一歩 ―
簿記の勉強を始めたきっかけは、人それぞれです。
上司に「経理の基礎は簿記だから」と勧められた人、転職やキャリアアップのために独学を始めた人、あるいは「数字に強くなりたい」という思いで挑戦した人も多いでしょう。
簿記を学ぶと、「財務諸表を読めるようになる」「経営を数字で理解できる」と言われます。
しかし、いざ合格しても——
「財務諸表を“読める”という感覚がわからない」
「損益計算書を見ても、何が良くて何が悪いのかピンとこない」
「数字をどう“使えばいい”のかわからない」
そんな悩みを抱えている人は、実はとても多いのです。
あなたが感じているその「使えなさ」は、努力不足でも理解力の問題でもありません。
それは単に、簿記の知識と実務で求められる“会計の使い方”の間に、橋がかかっていないだけなのです。
このシリーズ「簿記から“使える会計”へ」では、
簿記で学んだ知識を土台にしながら、“経営の言語”として会計を使いこなす力を、USCMA(米国公認管理会計士)の視点で解説していきます。
第1回のテーマは、「簿記の知識を経営の言語に変える」
ここでは、次の3つのことを中心に学びます。
- 簿記の本質的な役割 — 記録の正確さがなぜ経営の基礎になるのか
- 財務諸表を“数字の結果”ではなく“経営の物語”として読む方法
- 簿記で得た知識を、経営判断に使える思考に変えるステップ
つまり、簿記を“資格の知識”で終わらせず、
そこから一歩進んで「数字で語れる人」になるための第一歩を学びます。
目次
簿記が教えてくれるのは「数字の正しさ」

簿記検定で学ぶ内容は、会計の世界では欠かせない基礎です。
取引を正しく記録し、正しい財務諸表を作成する力。これは、すべての会計実務の土台です。
実際、企業の会計業務はこの「正確な記録」によって支えられています。
簿記がしっかりしていなければ、決算書も経営分析も成立しません。
簿記は“経営会話の文法”であり、その正確さは経営の信頼の源泉です。
しかし、実務で問われるのは、「数字をどう使うか」という次のステップです。
たとえば、売上が増えた・利益が減ったという結果を前に、経営の現場では「なぜ?」「どうすれば?」という“行動の判断”が求められます。
ここで登場するのが、「管理会計(マネジメント・アカウンティング)」の考え方です。
簿記が“過去を正確に記録する学問”なら、管理会計は“未来をつくるために数字を使う学問”です。
管理会計を体系的に学ぶ資格 ― USCMAとは
この管理会計を体系的に学べる国際資格が、USCMA(米国公認管理会計士:U.S. Certified Management Accountant)です。
USCMAは、アメリカの管理会計の専門資格で、経営判断・財務分析・戦略立案・予算管理など、企業の意思決定を支えるプロフェッショナルのために設計されています。
試験科目(シラバス)は大きく2つに分かれますが、そのうちPart 1は「財務計画・業績管理・分析(Financial Planning, Performance, and Analytics)」がテーマ。
簿記で培った「記録の力」を、“考える力”と“使う力”に発展させる構成になっています。
つまりUSCMAとは、「簿記のその先」を目指す資格。
単に帳簿を理解するのではなく、経営の言語として会計を使いこなすことを目的としています。
このシリーズでは、USCMAのシラバスを軸にしながら、簿記の知識を“実務で使える思考法”へ変えていきます。
財務諸表は「結果」ではなく「物語」
簿記で作成する財務諸表(P/L・B/S・C/F)は、一見するとただの数字の集まりです。
しかし、経営者やUSCMAの視点から見ると、それは企業の物語(ストーリー)です。
- 損益計算書(P/L)は、「どのように稼いだか」というストーリー。
- 貸借対照表(B/S)は、「どんな姿勢で戦っているのか」という経営の構造。
- キャッシュフロー計算書(C/F)は、「資金がどのように動いたか」という活動の軌跡。
たとえば売上が増加していても、B/Sを見ると在庫が膨らんでいる。
このとき、経営的には「売れていない在庫を積み上げているだけ」かもしれません。
このように、財務諸表の数字は結果ではなく、経営判断の痕跡。
数字は単なる集計ではなく、企業の「意思決定の履歴書」なのです。
簿記で学んだ勘定科目は、経営の行動を翻訳する“単語”です。
その単語を組み合わせて企業の文脈を読むこと——それが“数字を読む”という行為です。
この視点を持つと、会計の世界が急に立体的に見えてきます。
簿記の知識を「経営の問い」に変える
簿記の知識を実務で活かすためには、「なぜこの数字になったのか?」と問いを立てる力が欠かせません。
たとえば、売上総利益率(粗利率)が下がっていたとします。
簿記の知識だけなら、「原価が上がった」「売上が減った」といった表面的な説明に留まるでしょう。
しかし、管理会計の視点では、次のように考えます。
「変動費率が上がったのか?」
「固定費が増えて構造が重くなったのか?」
「販売構成が変わったのか?」
「価格戦略の結果なのか、コスト管理の問題なのか?」
同じ数字を見ても、問いの立て方が変われば、得られる答えも行動もまったく違います。
USCMAの思考法では、「数字の意味」を掘り下げることが出発点です。
簿記が「数字を正しく書く力」だとすれば、管理会計は「数字の背景を読む力」。
そしてそれを経営判断につなげるのが、USCMAの実務的役割です。
USCMAが重視する「数字を使う」3つのステップ
USCMAのシラバス(Part 1)では、単なる集計や報告よりも、数字をどう活かすかが中心テーマになっています。
その基本となる考え方が、次の3ステップです。
- 数字を整理する(Record) — 簿記で学ぶ領域。正しい記録がすべての出発点。
- 数字を意味づける(Analyze) — 分析・管理会計の領域。因果関係を読み解く。
- 数字で行動を変える(Decide) — 意思決定・戦略立案の領域。数字をもとに経営を動かす。
簿記を学んだ多くの人が①で止まっています。
しかし、経営の現場で求められるのは、②と③を行える人材。
USCMAは、この“数字を行動につなげる力”を体系的に鍛える資格です。
① 数字を整理する(Record)― 正確な記録はすべての出発点
まず欠かせないのが、簿記で培った「正確に記録する力」です。
取引を漏れなく、正しい勘定科目で記録すること。
それがなければ、いくら分析しても結論は誤ったものになります。
例えば、売上を「発生主義」で認識するのか、「現金主義」で見るのか。
在庫を正しく評価できているか。
こうした基本的な記録の精度が、後の分析の信頼性を決めます。
USCMAでも、外部財務報告(External Financial Reporting Decisions)がまず最初に学ばれます。
これは「経営判断を支える数字の土台を整える」ための段階。
数字を“整理する”とは、単なる入力作業ではなく、経営の地図を描く基礎工事なのです。
② 数字を意味づける(Analyze)― 「何が起きたのか」を読み解く力
次に求められるのが、整理された数字を「読む」力です。
ここで必要なのは、単に比率を計算することではありません。
数字の変化の背景にある“構造”を読み解くことです。
たとえば、売上が10%増えても、利益が減っているとき。
簿記の視点では「費用が増えた」で終わるかもしれませんが、
管理会計の視点では、「変動費率の上昇か」「販売構成の変化か」「固定費の増加か」を切り分けて考えます。
また、予算と実績の差(差異分析)を通して、「どの活動が成果を上げ、どの部門でコストが膨らんでいるのか」も明らかにします。
USCMAのシラバスでは、こうした分析を「Performance Management(業績管理)」や「Cost Management(コスト管理)」の中で扱います。
つまり、“数字の動きを経営活動に結びつける”ことがこの段階の目的です。
③ 数字で行動を変える(Decide)― 意思決定のための会計
そして最後のステップが、数字を「行動」に変える力です。
ここが、簿記と管理会計の最も大きな違いです。
管理会計では、数字をもとに「何をするか」を決めます。
典型的なのが、「意思決定会計(Decision Analysis)」です。
たとえば、
- 製品を値下げして販売数を伸ばすべきか?
- 外注すべきか、自社製造を続けるべきか?
- 設備投資の採算はどの水準で判断するべきか?
こうした問いに対して、USCMAは「関連コスト(Relevant Cost)」の概念を使って合理的に判断します。
つまり、“すでに発生した埋没原価”ではなく、“将来の行動によって変わるコスト”に注目するのです。
また、意思決定においては、数値だけでなく「リスク」と「戦略」のバランスも考慮します。
USCMAの試験では、単なる計算問題だけでなく、「どの選択肢が企業価値を最大化するか」という思考が問われます。
この段階に至って、ようやく数字は“報告”から“経営を動かす言葉”に変わります。
数字で語れる人になる
ここまで紹介してきた「数字を使う3つのステップ」――
- 正しく記録する(Record)
- 意味を読み取る(Analyze)
- 行動に変える(Decide)
この流れを実践できるようになると、数字はもはや「報告のための情報」ではなく、経営を動かす言葉になります。
そして、USCMAが最も重視するのは、まさにその先にある「数字で語る力」です。
簿記の段階では、数字は“過去を示すデータ”です。
しかし、管理会計の段階では、それを“未来をつくるストーリー”に変えていきます。
たとえば、あなたが経営会議でこう語る場面を想像してみてください。
「売上は前年より5%増えていますが、実は価格要因がマイナス3%、数量要因がプラス8%でした。数量の伸びは新規顧客獲得によるもので、来期は固定費吸収が進むため利益率改善が見込めます。」
このように数字を“説明”ではなく“物語”として語れるとき、
あなたは単なる経理担当者ではなく、経営の意思決定を支える存在になります。
数字で語れる人とは、単にデータを読み上げる人ではありません。
数字を使って「なぜ」「どうすれば」を導ける人のことです。
- 売上が増えた理由を、構成・価格・数量の要因に分解して説明できる
- 投資判断を、回収期間や内部収益率(IRR)などの根拠をもとに提案できる
- コスト削減の議論で、「どの固定費が筋肉で、どれが脂肪か」を論理的に説明できる
これらはすべて、「Record→Analyze→Decide」の3ステップの延長線上にあります。
数字を正しく整理し、その意味を読み解き、行動を決める――
その思考を積み重ねた結果として、「数字で語れる力」が自然に身についていくのです。
USCMAは、この“数字で語る力”を体系的に育てるための資格です。
USCMAの試験では、単なる計算問題だけでなく、「その数字をどう読み取り、どう行動すべきか」を問う実践的なケースが数多く出題されます。
だからこそ、USCMAを学ぶ過程では、次のような力が磨かれます。
- 数字の背後にある経営行動を想像し、仮説を立てる力
- 結論を「だからこうすべきだ」とロジカルに説明する力
- データを“伝わる言葉”に変える表現力
まとめ:簿記の知識を「使える会計」に変え、数字で語る力へ
簿記は、経営の「言語の文法」です。
正確に記録する力があるからこそ、企業の信頼も、分析の前提も成り立ちます。
しかし、USCMA(米国公認管理会計士)が重視するのは、その文法を使って「経営の会話をできるようになること」です。
簿記で学んだ“記録”を出発点に、
- 数字を整理し(Record)
- 数字の意味を読み取り(Analyze)
- 数字で行動を変える(Decide)
この3つのステップを踏むことで、数字は「報告」から「提案」へ、そして「過去の記録」から「未来をつくる言葉」へと進化します。
そして、その先にあるのが、「数字で語れる人になる」という到達点です。
数字をもとに現状を説明し、原因を見抜き、次の一手を示す。
簿記で培った知識を、経営を動かす思考に変えていく。
それが、あなたが次に踏み出す「使える会計」への道です。
このシリーズでは、そんな変化を一歩ずつ実感できるよう、次回から具体的なテーマ――経営レバレッジ、売上差異分析、Relevant Cost、ROE・ROIC分析――を通して、USCMAの考え方を実務に落とし込んでいきます。
🧩 次回予告
第2回では、「営業利益率の“落とし穴”――経営レバレッジで企業体質を読む」として、
簿記で学ぶ費用分類を、USCMA的に“固定費構造”の視点から読み解きます。