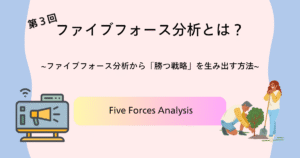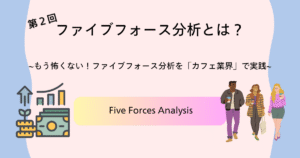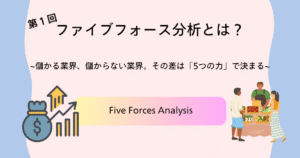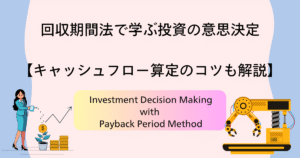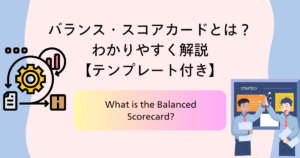― 過去の数字から、未来を描く力へ ―
第1回・第2回の続き:「知識を“使う”から、“未来を描く”へ」
このシリーズ「簿記から“使える会計”へ」では、簿記で学んだ知識を土台に、USCMA(米国公認管理会計士)が重視する“数字を活かす会計思考”を、実務の現場で使える形で学んでいます。
第1回では「簿記の知識を経営の言語に変える」ことをテーマに、数字を“記録”から“行動”につなぐ考え方を紹介しました。
第2回では「営業利益率だけでは見えない経営の筋肉」として、費用構造(固定費と変動費)から、企業の“体質”を読み解く力を身につけました。
そして第3回となる今回は、そこからさらに一歩進み、「数字を“予測”に変える会計思考」をテーマにします。
第3回では数字を“未来のために使う”ための考え方を学びます。
具体的には、次の3つが今回のポイントです。
- 予算(Budget)を、経営のシナリオとして描く方法
- 実績(Actual)を、現実の経営データとして読み解く方法
- 差異分析(Variance Analysis)を通じて、次の行動につなげる方法
つまり、今回は「数字をどう作るか」ではなく、「数字を使って、どう未来を描くか」がテーマです。
簿記で学んだ“過去の数字を整理する力”を、“未来の数字を設計する力”へ変えていく――
それが、この第3回の狙いです。
目次
数字は「結果」ではなく「未来の地図」

多くの人にとって、会計の数字は「過去の結果」をまとめた報告書です。
たしかに、決算書や損益計算書は「1年間の成果」を正確に示すもの。
しかし、管理会計の世界では、その数字を“未来を導く地図”として使います。
「もし売上が10%伸びたら、利益はどう変わるのか?」
「人件費を5%抑えたら、利益率はどう動くか?」
「新しい設備投資をした場合、損益分岐点はどこまで上がるのか?」
こうした“もしも”を数字で考えるのが、予測の会計(Forecasting)です。
数字を「過去の結果」として終わらせるのではなく、「これからを考える材料」に変える。
これが、USCMAが重視する未来志向の会計です。
予算(Budget)とは、「経営のシナリオ」である
未来の数字を扱う最初のステップが、予算(Budget)です。
多くの会社では「前年実績+α」で数値目標を決めますが、それだけでは単なる“積み上げ型の計画”にすぎません。
本来の予算は、
「経営戦略を数字で表現したシナリオ」です。
たとえば、経営方針として
「新商品で新しい市場を開拓し、売上を10%伸ばす」
という方向性があるとします。
その場合、数字に落とし込むべきは単なる“売上10%増”ではなく、
「どんな販売施策を打つのか」「そのために必要な費用はいくらか」
「生産体制は対応できるか」「利益率は維持できるか」――といった一連のシナリオです。
つまり、予算は「戦略を実行するための設計図」。
単なる数値目標ではなく、意思決定の前提を数字で描いたものなのです。
USCMAの試験範囲の中でも、Budgetingは「Planning(計画)」と「Forecasting(予測)」の中核領域です。
なぜなら、計画や予測は“作って終わり”ではなく、状況に応じて実行し、修正し、軌道に乗せていくための基準となるからです。
言い換えれば、数字を“立てる”こと自体よりも、立てた数字を使って意思決定を“動かす”ことにこそ意味があるのです。
実績(Actual)は「現実のデータベース」
予算という「未来の設計図」を描いたあとは、実際に動いた数字=実績(Actual)を把握します。
実績とは、日々の仕訳や決算処理の積み重ねそのもの。
簿記で学んだ基礎が、ここで「現実を映すデータベース」として活きてきます。
ここで大切なのは、数字を集めること自体ではなく、「現実と計画のズレをどう読むか」という姿勢です。
たとえば――
- 売上が予算を下回った → 数量が減ったのか?単価が下がったのか?
- 費用が増えた → 原材料の価格上昇か?作業効率の低下か?
- 粗利が悪化した → 商品ミックスの変化か?仕入先の条件か?
このように、数字のズレを“何が起きたのか”という視点で読み解く。
それが、次の「差異分析」につながります。
差異分析(Variance Analysis)は「経営のナビゲーション」
簿記を勉強すると、損益計算書を読めるようになります。
「売上が減った」「費用が増えた」「利益が落ちた」――こうした数字の動きは把握できる。
けれども、そこから先に進めず、「この数字をどう活かせばいいのか分からない」と感じる人は多いはずです。
実務で本当に求められるのは、
「なぜそうなったのか?」「次にどうすればいいのか?」
を数字で説明できる力です。
その“橋渡し”となる考え方が、差異分析(Variance Analysis)です。
📊「予定」と「現実」のズレを読む力
差異分析とは、予算(予定)と実績(現実)を比較し、ズレの原因を明らかにすること。
言い換えれば、経営の進むべき方向を教えてくれる「ナビゲーションシステム」です。
簿記では、「今期の結果」をまとめるのが目的ですが、差異分析は「どの要因が結果を変えたのか」を掘り下げます。
たとえば次のようなケースを見てみましょう。
| 区分 | 予算 | 実績 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,000 | 950 | ▲50 |
| 変動費 | 600 | 570 | ▲30 |
| 固定費 | 300 | 320 | +20 |
| 営業利益 | 100 | 60 | ▲40 |
利益が40減った。この「結果」だけを見ても、経営判断にはつながりません。
ここで大事なのは、「どこで、なぜズレたのか」を知ることです。
🔭差異を3つに分けるだけで、原因が見える
差異分析では、まず「ズレ」を3つに分類します。
- 売上差異(Sales Variance)
売上が下がったのは、数量が減ったのか、単価が下がったのか。
原因を分けることで、販売施策の見直しポイントが明確になります。 - 費用差異(Cost Variance)
費用が増えたのは、価格上昇によるものか、使いすぎたのか。
たとえば原材料単価の上昇なのか、歩留まりや効率の悪化なのかで、取るべき対策は異なります。 - 固定費差異(Fixed Cost Variance)
人件費・広告費など、固定費が増えたのは、計画外の支出か、投資判断によるものか。
「悪化」ではなく、意図的な成長投資の可能性もあります。
この3つの切り口で整理するだけで、利益の変化が「結果」から「構造」として見えてきます。
上記の差異のうち、今回は①売上差異(Sales Variance)に焦点を当て、実務でも使える形で解説していきます。
売上差異分析 ― 数字で「なぜ売上がズレたか」を説明する
月次報告で「今月の売上は予算を上回りました」と聞くと、一見うまくいったように見えます。
しかし、その“上回り方”を分析しないと、次の打ち手が見えてきません。
そのズレを構造的に理解するための手法として、売上差異分析(Sales Variance Analysis)が役立ちます。
売上差異とは、実際の売上と予算上の売上の差(ズレ)を分解して分析することです。
管理会計では、この差をいくつかの観点で切り分けます。
- 販売価格の違い(値上げ・値下げなど)
- 販売数量の違い(実際にどれだけ売れたか)
- 販売構成の違い(どの製品が多く/少なく売れたか)
これらを一つずつ分けて見ることで、「売上が上がった/下がった理由」を数字で説明できるようになります。
ステップ①:まずは基準を整える ― 固定予算と弾力性予算
売上差異分析では、次の2つの予算を使います。
| 予算の種類 | 意味 | 用途 |
|---|---|---|
| 固定予算(Static Budget) | 期首に立てた“理想の計画” | 実績との大きなズレを確認 |
| 弾力性予算(Flexible Budget) | 実際に売れた数量に合わせた“修正後の予算” | 数量ではなく価格や条件の違いを分析 |
差異は次のような関係で表せます。
固定予算差異 = 弾力予算差異 + 販売量差異
つまり、売上のズレには「価格の要因」と「数量の要因」があるということです。
ステップ②:差異の種類を理解する
売上差異には主に3つのタイプがあります。
| 差異の種類 | 意味 | 代表的な要因 |
|---|---|---|
| 販売価格差異(Selling Price Variance) | 実際の販売単価と予算単価の違い | 値引き、販売条件の変更、製品ミックス |
| 販売数量差異(Sales Volume Variance) | 売れた数量と予算数量の違い | 市場需要の変化、販売活動の強化 |
| 販売構成差異(Sales Mix Variance) | 製品ごとの販売構成比の違い | 高利益製品・低利益製品の比率変化 |
これらを合計すると、売上全体の固定予算差異(Static Budget Variance)になります。
ステップ③:実例で考える ― “値下げで売上が増えた”のは成功か?
たとえば、ある会社が商品Aを次のように販売していたとします。
| 予算 | 実績 | |
|---|---|---|
| 販売単価 | 1,000円 | 950円 |
| 販売数量 | 1,000個 | 1,200個 |
| 売上高 | 1,000,000円 | 1,140,000円 |
一見、「売上が140,000円も増えている」ので好調に見えます。
しかし、それは本当に営業の成果でしょうか?
差異を分解してみます。
| 差異の種類 | 計算式 | 金額 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 販売価格差異 | (950−1,000)×1,200 | ▲60,000円 | 不利(値下げ) |
| 販売数量差異 | (1,200−1,000)×1,000 | +200,000円 | 有利(数量増) |
| 合計(売上差異) | +140,000円 | 有利 |
結果として売上は増えましたが、実際には「価格を下げて販売量を増やした」結果です。
この数字を見れば、経営陣はこう考えられるでしょう。
- 値下げによって短期的には売上増を達成できた
- ただし、値引きによる利益率低下のリスクがある
- 今後は、販売数量の増加が利益にどれだけ貢献したかを検証すべき
このように、差異を分けることで“売上の構造”を見える化できるのです。
複数製品を扱う場合 ― 売上構成をチェックする

もし商品AとBを扱っている場合、売上差異の中でも特に重要なのが販売構成差異(Sales Mix Variance)です。
これは、売れた「合計数量」は同じでも、どの商品が多く売れたかによって利益が変わることを示す分析です。
例:A製品とB製品の販売構成が変わった場合
【前提条件】
| A製品 | B製品 | |
|---|---|---|
| 販売単価 | 1,000円 | 1,000円 |
| 変動費 | 600円 | 800円 |
| 限界利益 | 400円 | 200円 |
【販売計画(予算)】
当初の販売計画(予算)は、AとBを50:50の割合で販売する想定でした。
| A製品 | B製品 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 販売数量(予算) | 500個 | 500個 | 1,000個 |
| 売上高 | 500,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 |
| 限界利益 | 200,000円 | 100,000円 | 300,000円 |
【販売実績】
実際には、AよりもBの販売が増え、30:70の割合になったとします。全体の販売数量(1,000個)は同じです。
| A製品 | B製品 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 販売数量(実績) | 300個 | 700個 | 1,000個 |
| 売上高 | 300,000円 | 700,000円 | 1,000,000円 |
| 限界利益 | 120,000円 | 140,000円 | 260,000円 |
結果:数量は同じでも、利益は減った
全体の売上高は同じ1,000,000円。
それでも利益は300,000円(予算) → 260,000円(実績)に減っています。
なぜか?
利益率の高いAの販売が減り、利益率の低いBが増えたからです。
この差額(▲40,000円)が「販売構成差異(Sales Mix Variance)」です。
販売構成差異=製品構成比の変化によって生じた利益の変動
売構成差異の考え方を身につけると、「売上が同じでも、儲かり方は違う」という事実に気づけます。
- 売上増=利益増とは限らない
- 数量一定でも、構成が変われば利益は変わる
- 利益率の高い製品の構成比を維持・拡大することが、利益最大化のカギ
この視点を持つと、営業報告の「今月の売上は計画通りです」という一言の裏に、“本当に良い売上だったのか?”という問いを投げかけられるようになります。
数字を「記録」から「予測」に変えるために
予算(Budget)・実績(Actual)・差異分析(Variance)
この3つは、管理会計の基本サイクルです。
- 予算 … 未来を設計する
- 実績 … 現状を把握する
- 差異分析 … ズレから学び、次を改善する
この3つを繰り返すことで、数字は「過去の記録」ではなく「未来を動かす情報」に変わります。
すなわち、費用構造を理解し、予算と実績を比較し、差異を読み解くことで、数字は“未来を考える道具”に変わります。
- 数字で「過去を説明」するだけでなく、
- 数字で「次を予測」し、
- 数字で「意思決定を支える」
簿記で培った正確さが、ここで「洞察」に変わります。
つまり、
数字は、過去を語るものではなく、未来を導く言葉である。
この考え方を身につけることが、実務で会計を“使いこなす”第一歩です。
まとめ:数字で未来を描く力を身につけよう
これまでの3回で、
- 数字を「経営の言語」として使う力(第1回)
- 数字の「構造」を読み解く力(第2回)
- 数字で「未来を描く力」(今回)
を順に学んできました。
簿記を学んでも「実務で使えない」と感じる人が多いのは、数字を“結果”として見ているからです。
しかし、数字は本来、“行動の起点”であり、“未来の設計図”でもあります。
今回は、予算・実績・差異分析のサイクルの中でも、差異分析を中心に解説しました。
簿記の知識を実務で使える「経営を動かす知識」に変えたい人は、まずこの差異分析から始めることをおススメします。
数字の見え方が、確実に変わります。
- 変化の大きいところに絞る
すべてを分析する必要はありません。影響が大きい上位3項目を重点的に見るだけで効果があります。 - “勘定科目”ではなく“ビジネス要因”で考える
「広告費が増えた」ではなく、「顧客獲得単価が上がった」と言い換える。
経営と会話ができる言葉に変えることが大切です。 - ズレを数値で説明し、言葉で結ぶ
「費用が20万円増加した」ではなく、
「原材料単価が5%上昇したため、結果的に20万円の増加となった」と言えるように。
この“説明力”が、数字を使いこなす第一歩です。
🧩 次回予告
第4回では、「管理会計で鍛える意思決定力」として、Relevant Costを紹介します。
数字を使って経営をどう動かすか――“戦略の言語”としての会計を一緒に学びましょう。