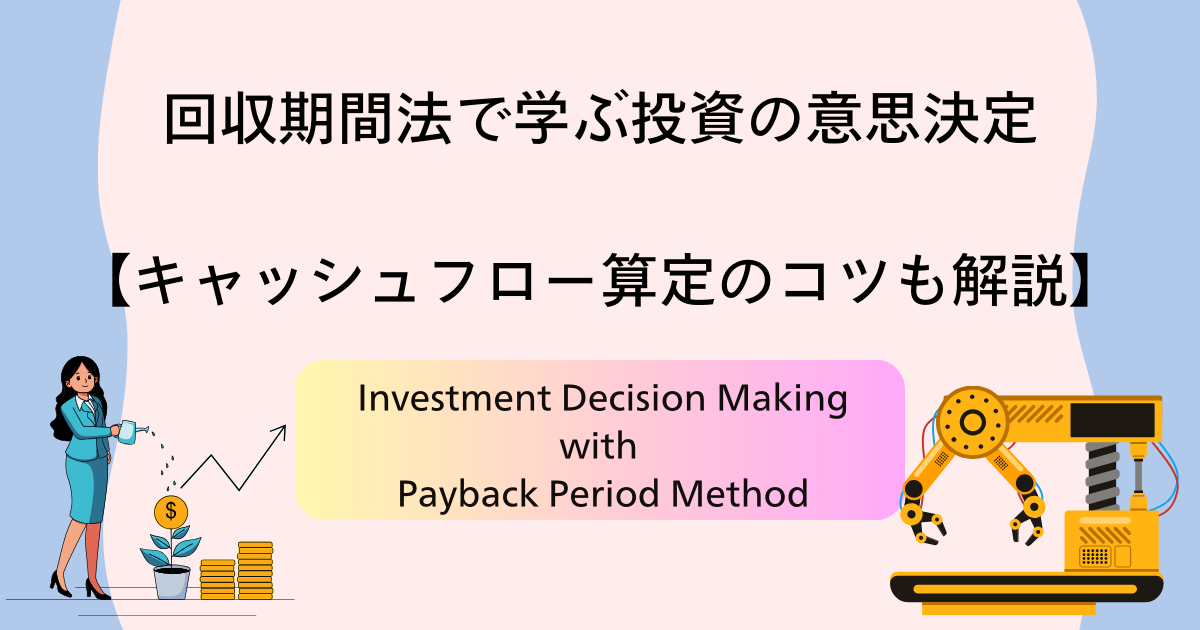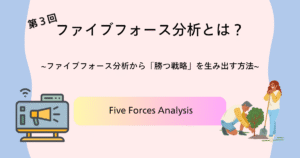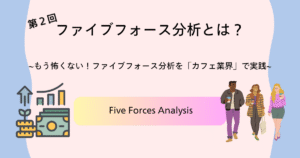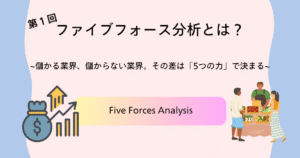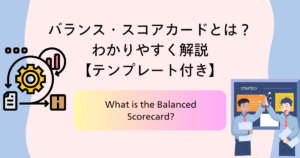こんにちは!USCMA(米国公認管理会計士)のKUNPEIです。
今回の内容は、設備投資やプロジェクト投資における意思決定の手法についてです。
「新しい機械を導入すべきか?」「新規事業に投資して大丈夫?」
ビジネスの世界では、日々、大小さまざまな投資の意思決定が求められます。しかし、多額の資金が動く投資は、その判断を間違えると企業の将来を大きく左右する可能性があります。
「なんとなく良さそうだから」といった感覚的な判断では、思わぬ落とし穴にはまることにもなりかねません。そこで、データに基づいて合理的な判断を下すための手法が重要になります。
この記事では、投資の意思決定に役立つ評価手法として、最もシンプルで分かりやすい「回収期間法」を解説していきます。

目次
投資の意思決定はなぜ重要?
投資とは、現在の資金を投じて、将来より大きなリターンを得ることを目指す行動です。例えば、設備投資なら生産効率の向上やコスト削減、新規事業投資なら売上拡大や市場シェア獲得が期待されます。
しかし、投資には常にリスクが伴います。期待通りのリターンが得られない可能性もあれば、予期せぬ問題が発生することも。だからこそ、闇雲に投資するのではなく、事前にしっかりと評価し、最適な選択をすることが企業の成長には不可欠なのです。
まずはここから!最もシンプルで分かりやすい「回収期間法」
投資の評価手法はいくつかありますが、最初に知っておきたいのが「回収期間法(Payback Period Method)」です。
これは、「投資したお金を、将来のキャッシュフロー(実際に入ってくるお金)で何年で回収できるか?」を計算する方法です。
非常に直感的で分かりやすく、投資の早期リターンや流動性を重視する際に役立ちます。
回収期間法の考え方
回収期間法では、投資によって得られる将来のキャッシュフロー(お金の入り)が、初期投資額(お金の出)をいつ上回るかを見ます。
- 計算式:
- キャッシュフローが毎年一定の場合: 回収期間 = 初期投資額 ÷ 年間キャッシュフロー
- キャッシュフローが毎年異なる場合: 累積キャッシュフローが初期投資額を上回る時点を算出します。
- 意思決定基準:
- 企業や経営者が設定した「許容回収期間」(例:3年以内、5年以内など)よりも短い期間で回収できる場合に、その投資を検討します。
- 複数の投資案件がある場合は、回収期間が最も短い案件を優先的に選択します。
回収期間法の計算例
ある会社で、新しい生産設備Aの導入を検討しています。
- 初期投資額: 1,000万円
- 期待される年間キャッシュフロー: 毎年300万円(5年間)
- 会社の許容回収期間: 4年
この場合の回収期間を計算してみましょう。
回収期間 = 1,000万円 ÷ 300万円/年 = 3.33年
結果: 回収期間は3.33年となり、会社の許容回収期間である4年よりも短いことが分かりました。
したがって、この設備投資Aは「投資しても良い」と判断できます。
次に、設備Bも検討してみます。
設備Bは、設備Aと違いの毎年のキャッシュ・フローが異なることを想定してます。
- 初期投資額: 1,200万円
- 期待される年間キャッシュフロー:下表のとおり
| 年 | 年間キャッシュフロー(万円) | 累積キャッシュフロー(万円) |
|---|---|---|
| 初期投資 | -1,200 | -1,200 |
| 1年目 | 200 | -1,000 |
| 2年目 | 400 | -600 |
| 3年目 | 300 | -300 |
| 4年目 | 400 | 100 |
初期投資額1,200万円は、3年目と4年目の間に回収されることが分かります。
3年目までの回収額:1,100万円(累積キャッシュフローが-300万円なので、あと300万円で回収完了)
残りの回収が必要な額:1,200万円 – 900万円 = 300万円
4年目のキャッシュフロー:400万円
4年目の回収期間を計算:300万円 ÷ 400万円 = 0.75年
回収期間 = 3年 + 0.75年 = 3.75年
結果: 回収期間は3.75年となり、設備Bも会社の許容回収期間である4年よりも短いことが分かりました。
設備Aと設備Bの回収期間はどちらも4年よりも短いため、どちらも投資しても良いと判断できます。
回収期間法のメリットとデメリット
メリット:
- シンプルで分かりやすい: 初心者でもすぐに理解し、計算できる。
- 流動性を重視: 投資した資金がどれくらいの期間で手元に戻るかを確認できるため、短期的な資金繰りを重視する場合に有効。
- リスクの把握: 回収期間が短いほど、有利と評価するため、不確実性の高い長期投資リスクを軽減できる。
デメリット:
- 貨幣の時間価値を考慮しない: 将来の100万円と今日の100万円の価値は同じではないという、「貨幣の時間価値」を無視しています。これは大きな弱点です。
- 回収期間後のキャッシュフローを無視する: 回収期間が過ぎた後に、どれだけ大きなキャッシュフローが生み出されるかを考慮しません。そのため、長期的に見て収益性の高い投資を見落とす可能性があります。
【実務の壁】将来キャッシュフローの算定をどう乗り越えるか?
回収期間法の理屈はシンプルで分かりやすいので、これまでの説明で計算方法は理解できたかと思います。
しかし、実務でこの計算を行うにあたって、多くの人が「難しい」と感じるのが、「将来のキャッシュフローをどうやって算定するのか?」という点でしょう。
確かに、未来の収入や支出を正確に予測することは容易ではありません。しかし、いくつかの基本的な考え方とアプローチを知っていれば、この「壁」を乗り越えることができます。
1. 「増分キャッシュフロー」の原則を理解する
まず大前提として重要なのが、「増分キャッシュフロー(Incremental Cash Flow)」を考えることです。
これは、「その投資を実行した場合と、実行しなかった場合のキャッシュフローの差額」を意味します。
既存事業の売上やコスト、あるいは投資とは無関係なキャッシュフローは含めません。
あくまで「その投資によって新たに入ってくるお金(収入)」と「その投資によって新たに出ていくお金(支出)」を特定するのです。
2. キャッシュフローの要素を分解する
将来のキャッシュフローは、大きく以下の要素に分解して考えます。
- 初期投資額(Initial Outflow):
- 設備の購入費用、設置費用、輸送費、据付工事費
- 初期運転資金の増加(例:在庫の増加、売掛金の増加など)
- 設備の売却による節税効果(投資の前に既存設備を売却する場合)
- 注意点:既に発生した埋没費用(Sunk Cost)は含めない
- 年間営業キャッシュフロー(Annual Operating Cash Flows):
- 収入の増加: 投資によって見込まれる売上増加分
- 費用の削減: 投資によって削減できるコスト(例:人件費、材料費、光熱費、修繕費など)
- 税金: 利益にかかる税金を考慮します。税引後のキャッシュフローが重要です。
- (収入増 + 費用減 – 減価償却費) × (1 – 税率) + 減価償却費で算出するのが一般的です。
- 減価償却費は非現金費用ですが、節税効果(Tax saving effect)を生むため計算に含めます。
- 最終キャッシュフロー(Terminal Cash Flow):
- プロジェクト終了時の設備の売却価格(残存価値)
- 運転資金の回収(プロジェクト終了に伴い、初期に増加した運転資金が回収される)
- 設備の撤去費用など
3. 算定のための情報源とアプローチ
これらのキャッシュフロー要素を具体的に算定するために、以下の情報源とアプローチを活用します。
- 社内データと担当者へのヒアリング:
- 過去の同種プロジェクトのデータ(あれば)
- 営業部門:新製品の売上予測、市場規模
- 製造部門:生産量、歩留まり、材料費、既存設備の維持費、新設備の電力消費量
- 経理部門:減価償却方法、税率、過去の類似費用の実績
- 購買部門:設備・材料の調達価格
- 人事部門:人件費の変動
- 市場調査とベンチマーク:
- 業界レポート、市場調査会社のデータ
- 競合他社の事例、公開されている情報
- 設備メーカーからの性能データや運用コスト情報
- 複数のシナリオを想定する(感度分析・シナリオ分析):
- 「最良ケース」「標準ケース」「最悪ケース」など、複数のシナリオでキャッシュフローを算定します。
- 各シナリオでの回収期間を計算し、リスクの幅を把握することで、より現実的な意思決定ができます。
- 例:「売上が予測より10%少なかったら?」「原材料価格が5%高騰したら?」といった変動要因を考慮します。
- 専門家やコンサルタントの活用:
- 特に大規模な投資や、専門的な知識が必要な分野(例:特定技術の将来性予測)では、外部の専門家やコンサルタントの知見を借りることも有効です。
- 仮定(Assumption)を明確にする:
- 予測には必ず「仮定」が伴います。「この売上は、市場が〇%成長するという仮定に基づいている」「このコスト削減は、設備が〇年間故障しないという仮定に基づいている」など、どんな仮定の上に数字が成り立っているかを明確にし、文書化しておくことが重要です。後で検証する際に役立ちます。
【例】設備導入によるコスト削減効果のキャッシュ・フロー算定
ある会社が、既存の生産設備を新型設備に置き換えることを検討しているとします。
- 初期投資額:
- 新型設備購入費:750万円
- 設置工事費:50万円
- (既存設備の売却益:なし)
- 初期投資額合計:800万円
- 年間営業キャッシュ・フロー(CF):
- 人件費削減効果: 年間200万円(新型設備導入で必要な人員が減少)
- 電力費削減効果: 年間30万円(新型設備は省エネ性能が高い)
- 材料費削減効果: 年間10万円(歩留まり改善による)
- 年間減価償却費: 160万円(耐用年数5年・定額法)
- 法人税率: 30%
- 計算式
- 年間税引前利益増加額(税効果のある部分) =(200+50+10)−100=160万円
- 税引後の利益増加額 =160×(1−0.30)=112万円
- 税引後CF増加額 =112+100(減価償却費は現金支出を伴わない費用であるため加算)=212万円
- 年間CF:212万円
- 最終キャッシュ・フロー:
- 5年後の売却価格:50万円(簿価0)
上記のキャッシュ・フローの算定例を表にしてみましょう。
| 0年目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | ||
| ①初期投資 | -800 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ②設備売却額 | ー | ー | ー | ー | ー | 50 | |
| ③人件費削減効果 | ー | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| ④電力費削減効果 | ー | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| ⑤材料費削減効果 | ー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ⑥削減効果合計: ③~⑤合計 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| ⑦減価償却費 | ー | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| ⑧税引前利益増加額: ②+⑥-⑦ | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | |
| ⑨法人税等:⑧×30% | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 39 | |
| ⑩税引後利益増加額: ⑧-⑨ | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 91 | |
| ⑪年間営業CF:⑩+⑦ | -800 | 216 | 216 | 216 | 216 | 251 | |
| ⑫累計営業CF:①+②+⑪ | -800 | -584 | -368 | -152 | 64 | 315 | |
- 初期投資額(Initial Outflow):
- 設置工事を含め、新しい設備導入にかかる費用をすべて含める
- 既存の設備にかかる費用は含めない
- ただし、既存設備の売却による収入がある場合は、含める
- 年間営業キャッシュフロー(Annual Operating Cash Flows):
- 今回の設備例では、新しい投資による売上高の変化はないため、売上高はCFの計算に含めない
- 利益にかかる税金を考慮する
- 減価償却費は支出を伴わない費用であるため、営業CFの算定は税引後利益に足し戻す
このように各要素を分解し、根拠となる情報を集めることで、より実態に即したキャッシュフローの算定が可能になります。
ちなみに、この例の回収期間を計算すると以下のとおりです。
回収期間 = 3年 + 0.29年(64÷216) = 3.29年
まとめ:投資の第一歩は「回収」から!
今回の記事では、投資の意思決定における最も基本的な評価手法である「回収期間法」について解説しました。
確かに、回収期間法には貨幣の時間価値を考慮しない、回収期間後のキャッシュフローを無視するといったデメリットがあります。そのため、この手法だけで大規模な投資を最終決定するのは避けるべきでしょう。
したがって、投資判断の精度をさらに高めるためには、回収期間法だけでは不十分な点もあるため、次のステップとして、貨幣の時間価値を考慮した「正味現在価値法」や「内部収益率法」を学ぶ必要があります。
ぜひ、この回収期間法を足がかりに、データに基づいた合理的な投資意思決定のスキルを身につけて、ビジネスの成長に貢献してください。