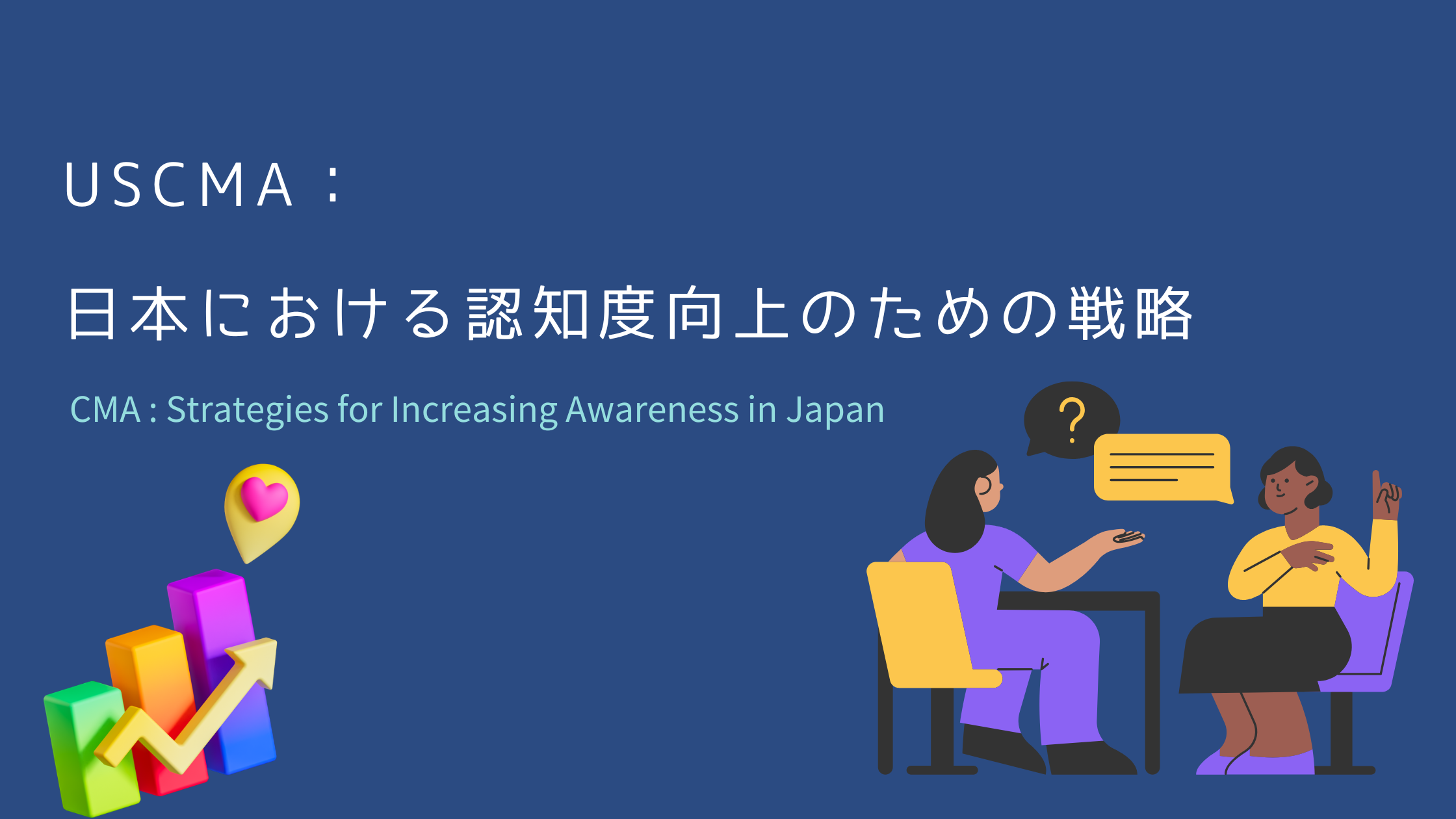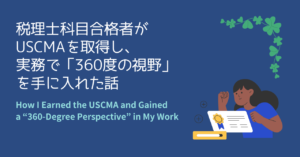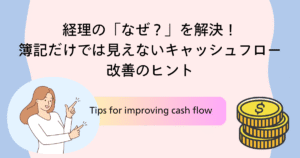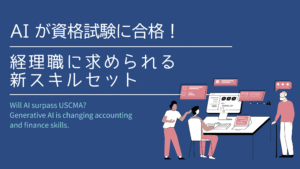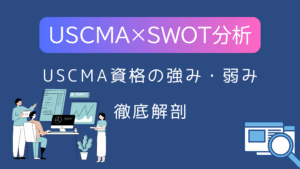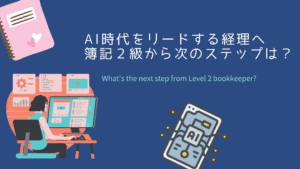こんにちは、USCMAのKUNPEIです!
先日、2025 年6月より USCMA(米国公認管理会計士)の日本語試験が新たに実施されることが発表されました。
日本語試験の導入は、日本における管理会計学習の機会を広げる上で、非常に意義深い出来事です。
これを機会に、日本企業における管理会計プロフェッショナルを支援するための体制が整備されていくことを期待します。
そもそもUSCMAは、管理会計と企業財務における世界標準に適合する卓越した専門性を証明する資格として、国際的には長年にわたり広く認知されてきました。
一方で、日本では十分に認知されているとは言いがたいのが、率直な感想です。
わたしは、USCMAを取得して以来、当ブログを通じてUSCMA資格の情報・魅力について紹介してきました。
今回は、日本語での受験が可能となったことを歓迎し、USCMAの日本におけるさらなる知名度向上のための戦略を個人的な見解ではありますが以下に述べたいと思います。
ターゲット層へのアプローチ
- 企業の人事・研修担当者への働きかけ:
- USCMAが企業の財務戦略や業績管理にどのように貢献できるかを具体的に説明し、研修プログラムへの導入を提案する。
- 企業の人事評価制度にUSCMAの資格を組み込むよう働きかける。
- 大学・大学院のキャリアセンターへの情報提供:
- USCMAがグローバルなキャリアパスにどのように役立つかを説明し、学生への情報提供を依頼する。
- 会計・ファイナンス系の学生団体と連携し、USCMAに関するセミナーやワークショップを開催する。
- 会計・コンサルティング業界へのアプローチ:
- USCMA資格保持者の専門性をアピールし、採用時の優遇措置を促す。
- 業界団体と連携し、USCMAに関するイベントや研修プログラムを開催する。
USCMA(米国公認管理会計士)の日本における認知度を高めるためには、様々な戦略が考えられますが、まず重要な鍵を握るのが、ターゲット層への的確なアプローチです。
なぜなら、資格の価値を最も理解し、その恩恵を受ける可能性の高い層に情報を届け、共感を広げていくことが、認知度向上への最も効率的な道筋となるからです。
その中でも企業への働きかけは、まず実施すべきです。やはり企業が必要とする専門性を持った資格であることを理解してもらうことで、初めてこの資格を持った人材への需要へとつながります。
近年、経理・財務部門に期待される役割りは変化しています。日本企業のグローバル化に伴い、経営課題がますます複雑化する中で、ただ的確に決算処理や税務申告をする能力だけでは通用しません。
経営の羅針盤として会計・財務などの知識をバックグラウンドに、企業の課題解決に役立ち、競争力や収益性向上の源泉として機能する人材、組織が求められています。
いわゆるFP&A(Financial Planning & Analysis)組織です。しかし、日本企業においては、FP&Aを担える人材、組織が不足しています。
特に経営層は、この現状と理想とのギャップを感じてる方が多いです。※
USCMAはそのギャップを埋める人材であることを経営層にも積極的にアピールすることで、潜在的な需要を掘り起こすことができます。
※KPMGジャパンの調査によると「FP&A機能の強化に関心はあるが、具体的な取組みを進めていない」という回答が2023年の調査と同じ5 6%となっており、日本企業においてFP&A機能の強化の取組みが進捗していない状況が浮き彫りとなりました。
出所:「KPMGジャパン CFOサーベイ2024」
KPMG
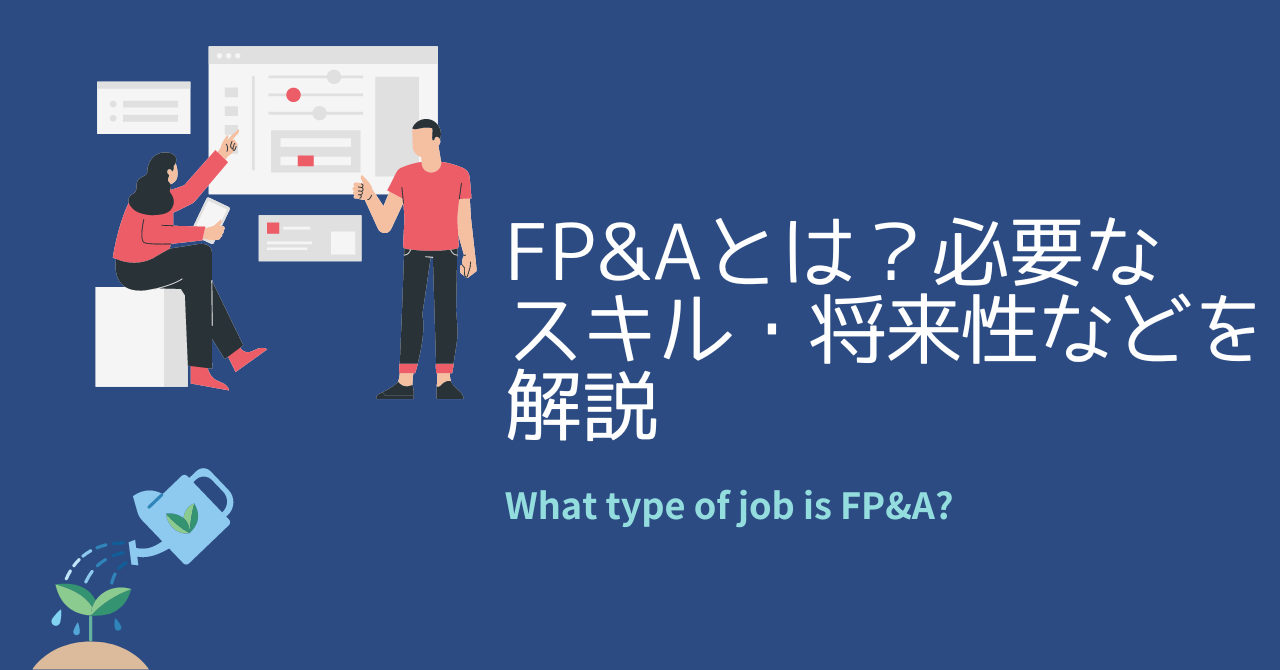
日本語での情報発信の強化
- 日本語での情報提供の充実:
- USCMAの公式サイトや学習教材の日本語翻訳を拡充する。
- USCMAに関する日本語の書籍や記事を増やし、情報へのアクセスを容易にする。
- オンラインでの情報発信:
- USCMAに関するウェブサイトやSNSアカウントを開設し、積極的な情報発信を行う。
- USCMA取得者の体験談やキャリアパスを紹介する動画コンテンツを制作・公開する。
- セミナー・イベントの開催:
- USCMAに関するセミナーやワークショップを定期的に開催し、資格の魅力を直接伝える。
- 会計・ファイナンス関連のイベントにUSCMAのブースを出展し、認知度向上を図る。
情報発信の強化こそが知名度を上げる上で一番重要と考えます。現状は日本語での情報提供が十分とはいえない状況です。
IMA® (Institute of Management Accountants、米国管理会計士協会)のサイトは英語での表記です。ただIMAのサイトには、日本のセクションがあり日本語で記載されているものの情報量が少ないのが現状です。そのため日本語サイトを立ち上げ、日本語でのUSCMAの情報の充実が必要です。
さらに、日本語サイトにアクセスするきっかけとなるように、XやInstagramなどのSNSで情報を発信し、サイトへの集客を図るべきです。
また、会計関連の情報誌への記事の掲載も有効な手段と考えます。
記事の内容は、USCMAの情報というより、USCMA資格保有者による管理会計などの解説記事を掲載し、間接的にUSCMA資格の存在を知ってもらう。経理部門の実務家が日常的に目にするような雑誌に投稿して、USCMAを身近に感じてもらうことを狙います。
ターゲット層へのアプローチという意味でも、実務家に人気の税務研究会が発行している経営財務で、初心者向けの管理会計を解説するのが最適ではないでしょうか。
USCMA受験・学習環境の整備
- 日本企業におけるUSCMA資格保持者の活躍事例の紹介:
- USCMA資格保持者が日本企業でどのように活躍しているかを具体的に紹介し、資格の有用性を示す。
- USCMA資格保持者のキャリアアップ事例を紹介し、資格取得のモチベーションを高める。
- USCMA資格保持者のコミュニティ形成:
- USCMA資格保持者向けの交流会や勉強会を開催し、情報交換やキャリアアップの機会を提供する。
- USCMA保持者のネットワークを構築し、USCMAの価値を高める。
- 日本におけるUSCMA試験の利便性向上:
- 試験会場の増加や試験日程の柔軟化など、受験しやすい環境を整える。
企業等で活躍している資格取得者の生の声や事例を紹介することでUSCMA資格を取得後、どのようなキャリアを描けるのか、具体的イメージを持つことができ、USCMA受験への意欲が増すのではないでしょうか。
また、試験日程は、受験できない月が設定されていますが、テストウインドウ内においては、テストセンターの空席があれば、土日祝日を問わず予約・受験が可能なため、ある程度の柔軟性があります。
一方で、受験できる会場が、国内では東京と大阪のテストセンターの2カ所と限られているため、受験会場を増やすことやオンライン受験を可能とするなどで、受験しやすい環境を整えることが必要と考えます。
(2022年1月 自宅受験(Remote Testing)が可能になりましたが、現在中止されている。)

まとめ:日本企業の国際競争力強化、個人のキャリアアップへの貢献に期待
USCMAの日本における知名度向上は、単なる資格の普及に留まらず、日本企業の国際競争力強化、個人のキャリアアップ、そして管理会計プロフェッショナルの育成という多岐にわたる意義を持ちます。
本稿で述べた戦略は、的確なターゲット層へのアプローチ、日本語での情報発信の強化、そして受験・学習しやすい環境整備による受験へのモチベーション向上という三つの柱を中心に構成されています。
これらの戦略を複合的に展開することで、USCMAの日本における認知度は着実に向上していくと確信しています。
USCMA資格が個人のキャリアアップと日本経済のグローバル化に貢献することを期待し、今後の展開を注視しながら、本ブログを通じて情報発信を続けていきたいと思います。